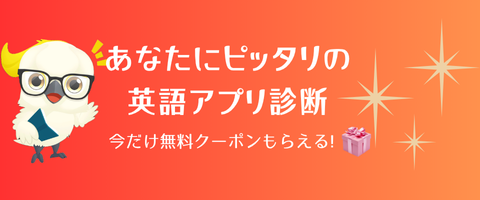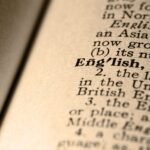辞書や教科書に当たり前のように掲載されている発音記号は、刺身の妻の
ようにあしらいとしてしか見られていないかもしれませんが、実は、英語
音声の正確な理解と再現を可能にする有効な手段です。しかし、発音記号
をうまく活用していない人が多いように見受けられます。発音記号は正し
い発音への近道です! 音声を耳でまねるだけでなく、記号の意味を知る
ことで、自分の発音を確かめたり直したりできるようになります。
現在の発音記号が考案され、英語教育に取り入れられ、大きな成果をあげ
て確立する過程には、1 人の人物を巡る壮大なドラマがありました。
ドラマの主演は、ロンドン大学に音声学科を創設したダニエル・ジョーンズ
(Daniel Jones)。そして助演は 3 人。(1) ジョーンズにフランス語音声学
を伝授し、国際音声学会 (International Phonetic Association、 以下 IPA) を
設立した、ソルボンヌ大学(パリ大学)のポール・パシー (Paul Passy)。
(2)ジョーンズが通ったパブリック・スクールの校長で、ジョーンズの活動を
多方面から支援したアーネスト・R・エドワーズ (Ernest R. Edwards)。
(3)ジョーンズの下で彼の発音記号を学び、1922 年に文部省英語教育顧問とし
て来日し、14 年間日本の英語教育の発展に寄与したハロルド・E・パーマ
ー (Harold E. Palmer) の 3 人です。
1. ダニエル・ジョーンズ登場前夜
ロンドン大学には、ジョーンズ以前にも音声学の授業がありました。最も
古い記録は、ジョーンズよりも約 40 年前の 1864 年で、内容は「雄弁術」
の よ う で す 。また、電話を発明したアレクサンダー・グラハム・ベル
(Alexander Graham Bell) の父親で、言語学者のアレグザンダー・メルヴィル
・ベル (Alexander Melville Bell) も 1866 年に音声学を講義しています。
その内容は「朗読法」でした。メルヴィル・ベルは「可視音声、視話法」
(Visible Speech) という発声器官の形や動きを図示した発音記号を考案し
て、Bell (1867) を出版しました。
ジョーンズが通ったパブリック・スクール (University College School) は
ロンドン大学 (University College) の一部であって、同じ敷地内にありました。
ジョーンズはケンブリッジ大学(数学科)へ進学しましたが、校長だった
エドワーズは、パシーの指導の下、「日本語の音声学的研究」という論文を
ソルボンヌ大学へ提出し、1903 年に博士号を取得しました。そして、1903年
から 1905 年にかけて、ロンドン大学でフランス語音声学を教えています。
エドワーズは 11 歳までの幼少期を日本で過ごしたので、日本語が堪能でした。
エドワーズ自身も音声学者として、IPA の「音声学習熟度検定」(Certificate
of Proficiency in the Phonetics of English/French/German) の制度構築に尽力
しました。ちなみに 1908 年にロンドン大学を会場として開始されたこの
検定試験は、受験者が徐々に減少し、ついに 2023 年、世界中の多くの大学
で音声学の講義が開講されているという理由から 115 年の歴史に幕を閉じ
ました。
ジョーンズは 1905 年の秋にパリへ赴き、パシーの自宅を訪問し、それ以後、
終生絶えることのなかった音声学研究への情熱に火がつきました。
ジョーンズは、パリでパシーの指導を受けることにして、パシーの妹のモッ
ト家に下宿することにしました。これが縁となって、1911 年にパシーの姪
シリル・モット (Cyrille Motte) と結婚しました。
エドワーズはこの年 (1905 年) 教育省の教育視察官 (Inspector of Schools)
に任命されて、大学を離れました。音声学の授業は、ドイツ語学科の R・
A・ウィリアムズ (R. A. Williams) に引き継がれ、ウィリアムズは、英語と
ドイツ語に焦点を当てた音声学の講義を行いました。これがロンドン大学
で初めての「英語音声学」の講義になります。ところがウィリアムズは、
1906 年末にダブリン大学へドイツ語学科長として転出してしまいます。
2. ジョーンズの登場と音声学の発展
ウィリアムズがロンドン大学を去った後、ジョーンズに白羽の矢が立ちま
した。エドワーズが大学当局にジョーンズを音声学の講師に推薦してくれ
たのです。1907 年 1 月、26 歳のジョーンズは週 1 コマ、フランス語音声学
の臨時助教 (temporary assistant teacher) になりました。受講生は 18 名の夜
間クラスで、全員がロンドン市内の中高の教員でした。
ジョーンズの授業は、理論 (theory) と発音練習 (practice) が両輪となって
いて、講義と演習に半分ずつの時間が割かれていました。演習では、発音記号
を 使っ た「 発音書き 取り 」 (phonetic dictation) と「 聴取練習 」 (ear-
training) が中核となっていました。「発音記号の音読」(phonetic reading) も
行われました。発音記号を読んで、音声を再現する練習です。初めの学期
の受講生たちは自発的に、次の学期にも授業を継続してほしいと要望しま
した。この要望を大学当局も受け入れて、ジョーンズはフランス語学科の
中で独自の「音声学」講座を非常勤講師として担当することになります。
聴取練習でも、母語とは異なる音を正確に聴き分ける力を養成するために
発音記号が利用されました。「最小対」(minimal pair) や「無意味語」
(nonsense word) も使われました。無意味語は、ターゲット言語の音、及び
音節構造を用いて作成するので、その言語らしく聞こえますが、綴り字や
意味の知識を排除できるので、トレーニングには最適です。そして、
その発音記号もジョーンズ自らが改良したものでした。
近年では多少修正されましたが、今でも世界中の外国語教育で使われています。
日本の英和辞典にも載っている発音記号の基となるものでした。
ローマ字を応用した発音記号は彼以前にもありました。まず、19 世紀前半
に綴り字をシンプルに改革しようという流れの中で生まれた「表音記号」
(phonotypic alphabet) が挙げられます。次にジョーンズの直近では、オック
スフォード大学のヘンリー・スウィート (Henry Sweet) が考案した「ロー
ミック記号」(Romic) がありました。しかし、th 音を [th、 dh] (例:<this>
[dhis])で表記したり、母音は正確さにこだわって、表記が複雑になったり
していました。それをジョーンズは、最初から現在の記号に近いものに改
良して使用しました。そのおかげで発音記号は急速に普及しました。
ジョーンズの授業と発音記号、そして研究業績は高く評価されました。
音声学の講義を始めてから 2 年で、英語音声学の体系的な概説書を執筆し、
Jones (1909) として出版しました。また、1907 年以来、毎月 1、 2 本の論文
を IPA の機関誌に発表していました。1911 年には、年に 22 本の論文を公
表しています。
劇作家のジョージ・バーナード・ショー (George Bernard Shaw) は、ジョー
ンズ を 主人 公ヒ ギ ンズ 教 授の モデ ル とし て 『ピ グマ リ オン 』
(Pygmalion,1912) という戯曲を仕上げました(『マイ・フェア・レディ』の原作)。
ロンドン大学にはショーから音声分析のための実験機材が提供されました。
ジョーンズは 1912 年に専任講師となり、「音声学科」(the Department of
Phonetics) を世界で初めて独立した学科として、ロンドン大学に創設し、
学科長 (department head) になりました。 大 学 評 議 会 (the College
Committee) は、ジョーンズの音声学科を「すべての語学科にとっての貴重
な補助部門」(valuable auxiliary to all the Language Departments) と認めてい
ました。
第一次世界大戦中にも研究と執筆を続け、上流階級の社会方言である「パ
ブリック・スクール発音」(1927 年にイギリスでラジオ放送が開始されて
からは BBC の標準発音)をジョーンズ式発音記号で記述した英語発音辞典
(Jones, 1917) を出版しました。また、Jones (1918) では、20 世紀の音声学
が飛躍するための 1 つの土台となった「基本母音」(Cardinal Vowels) の着
想を詳細に発表しました。
彼は 1915 年に上級准教授 (reader)、1921 年に教授に昇格し、1949 年に定
年退職するまでの 37 年間、音声学科長の職務を続けました。IPA でも 1927
年から 1949 年までの 22 年間、事務局長を務め、定年後の 1950 年から 1967
年に他界するまでの 17 年間は、会長として音声学の発展に大いに貢献しました。
3. 発音記号を使ったジョーンズの指導法
ジョーンズの指導法はとても単純で、簡単なものです。「発音書き取り」
(phonetic dictation) は、読み上げられた単語や文を発音記号で書き取るだ
けです。「発音記号の音読」(phonetic reading) は、その書き取った発音記号、
あるいは別の教材、つまり発音記号で書かれた語句や文を、声に出して読
み上げるだけです。その時に英語として正しく発音されていなければ、発
音が丁寧に矯正されます。
「聴取練習」(ear-training) は、上記の発音書き取りに加えて、「最小対」
(minimal pair) で示された単語のうち、どちらが発音されたかを判断したり、
イントネーションの「トーン、音調」(tone) を発音記号(補助記号)で書
き取り取ったりするものです。初めは難しく感じるかもしれませんが、慣
れれば、ear-training の文字通り、聴覚が訓練されて、正確に判断できるよ
うになります。英語の場合、トーンに意味的な機能があるので、この能力
は必要です。
このような指導法は、現在でもロンドン大学の「英語音声学サマー・コース」
(Summer Course in English Phonetics, SCEP [skep]) で実践され続けています。
Jones (1917 & 1918) の出版後、1919 年に SCEP が開始され、100 年
以上続いています。世界中から多くの英語教員や学生が参加しました。
ジョーンズの英語音声学は、ハロルド・E・パーマーの「オーラル・メソッ
ド」(oral method) にも取り入れられていました。パーマーは、来日前の 1915
年から助教 (assistant) として、ジョーンズの下で音声学科の授業を手伝っ
ていました。
パーマーのオーラル・メソッドは、当時フランスやドイツで流行っていた
「ダイレクト・メソッド」(ベルリッツ方式)を日本向きにアレンジしたも
のですが、発音記号を使ったジョーンズの指導法も重視したものでした。
このように大正時代に輸入された発音記号は、出版物には広く掲載されて
いますが、効果的に利用されていないような気がします。発音記号の習得
は学習者への負担が大きいとか、入試問題には使われないとか、教師側に
音声学の知識が必要であるとか、理由は容易に推測できます。
しかし、発音記号を覚える負担は、心配するほど大きくありません。英語
には子音が、24 しかありません。しかもその発音記号の半分以上はローマ
字と同じです。母音は、アメリカ英語では 15(地域によっては 16)、イギ
リス英語では 20 です。
発音記号は綴り字よりもシンプルです。発音記号を覚えて、発音練習をし
てみましょう。子音の後に余計な母音を付けていないか、母音の発音が日
本語の母音になっていないか、自分の気付きが発見できます。視覚的に母
音や子音を意識して練習できます。
自分で発音できない音は聴き取れません!
英語の発音が身に付けば、話す英語がよく通じるようになります。自信を
もって英語が話せるようになります。発音練習はすぐに効果が実感できま
す。そして、練習すればするほど上達するので、楽しく続けられます。
参考文献
Bell、A. M. (1867). Visible Speech: The Science of Universal Alphabetics.
London: Simpkin Marshall.
Collins, B. & Mees, I. M. (1999). The Real Professor Higgins: The Life and
Career of Daniel Jones. Berlin: Mouton de Gruyter.
Harte, N. & North, J. (1991). The World of UCL: 1828—1990. London:
University College London.
Jones、 D. (1909). The Pronunciation of English. Cambridge: The University
Press.
Jones, D. (1917). An English Pronouncing Dictionary. London: J. M. Dent.
Jones, D. (1918). An Outline of English Phonetics. Leipzig: Teubner.