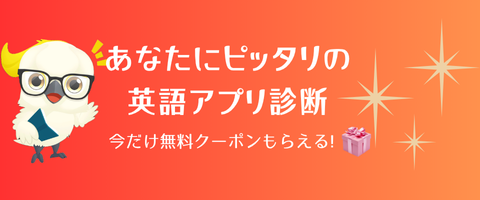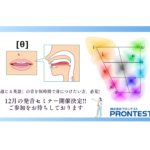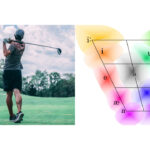「音符の読めないアメリカ人」というのは、
ちょっと叱られそうですね。
でも、ここには日本の英語教育を考えるうえで深い意味が隠れています。
最後までおつき合い下さい。
◆英語教育を見つめなおした半年間
実はこの半年ほど、ブログやメルマガの更新を控え、
英語教育の現状をじっくり考えていました。
果たして学習者が本当に求めているのは「通じる発音」なのだろうか。
世の中の流れを見ていると、どうも、
「発音練習を省こう」という方向に傾いているように感じられたのです。
翻訳機やAI通訳があれば旅行程度は事足りるし、
確かにある意味、コミュニケーションはできますよね。
それから、お聞きになったこともあるでしょうが、
Englishese という表現もあって、
世界にはシンガポール英語やインド英語のように、
それぞれの発音が市民権を得ている実例もあります。
確かに「どんな英語でもいい」という考え方は理解できます。
しかしその裏には必ず「通じれば」という条件がつくはずです。
◆教育現場で繰り返される言葉
教育委員会や先生方と話すと、「今も昔と同じフレーズ」を耳にします。
・自由会話を取り入れよう!
・発音は気にしなくてもいい、まずは話すことが大事。
・楽しく英語を口に出すことから始めよう。
確かに楽しさは重要です。
しかし「自分は英語を話しているつもり」で一方的に発するだけでは、
本当の意味でのコミュニケーションとは言えないのではないでしょうか。
◆学会の変化と「通じる発音」の再評価
私が所属している発音に関する学会では、昨年までは、
「どんな発音でも構わない」という意見も目立ちましたが、
今年は少し空気が変わっていたように感じました。
「やはり通じる発音は大切だ」とする先生方が増え、
その中で「発音記号どおりに読めること」が、
「通じる英語」の基本である、という認識が
共有されつつあるように感じました。
音声に関する学会は、専門的な研究を「掘り下げる」場であって、
必ずしも「通じる英語」について議論する場とは限らないのですが、
それでも自然とこうした方向に議論が流れているのは興味深いことです。
◆日本の英語教育が歩んできた道
1988年に、
プロンテストの前身である英会話スクールをつくばに開いたころ、
全国の小中学校にはネイティヴの先生が何万人もやってくるから、
これで「日本人も英語を話せるようになる」と
人々は期待しました。
今でいうALTの先生のことです。
一気に英会話熱も高まりました。
しかし、時を経ても教育現場において「日本人の英語力」は
大きくは変化しませんでした。
中学校の英語の教科書から「発音記号」も消え、
大学の教育学部からさえ「発音指導」は消えていきました。
しかし、そうした流れの中で、
次にはなんと「小学校から英語を教えよう」と、
小学校英語が何年もの準備期間を経て開始されます。
中学校の先生のなかにも、教育学部で「音声学」を教わらないために
発音指導をあまり受けてこられなかった先生も多くおられたようです。
特に、小学校の先生たちが英語を教えるのは、当初、
英語を教えることになるなんて予想もしていなかった先生方が
多かったという背景もありまして、準備段階から、正直なところ、
予想以上に難しかったはずだと思います。
その結果、小学校での英語の授業の正式導入に先行して、
塾やスクールなど「学校の外」で英語学習の低年齢化が進みました。
結果として「通じる発音」を身につけるかどうかは、
たまたま出会った指導者に左右されるという、
不公平な状況も生まれました。
ちなみに、弊社プロンテストが、
最初の発音矯正ソフトウェア開発を始めたのは2004年です。
2008年の初期の商品化において、最初の対象は「高校生以上」でした。
発音練習はリスニングに効果があるという検証がされたのは、
2010年ごろのことでした。
そしてそれから15年がたちました。
今やAIが英語教育に導入されています。
しかし「AIと自由会話すれば自然に英語が身につく」と
本気で信じるのは危険です。
実際には、AIと会話するにも
「発音の明瞭さ(intelligibility)」が欠かせず、
そこが欠けると会話自体が成立しません。
たとえばオンラインで海外の教室と「国際交流」という場をつくり、
会話をさせる試みも多く聞かれるようになりました。
生徒達は、英語を楽しく話せていると聞いています。
それはそれで、とても大切なことです。
しかし、そこで「通じる音」として十分な訓練がされないと、
やはり「ノンネイティヴ」の生徒同士の会話が
成立していないという問題をよく耳にします。
◆「音符が読めないアメリカ人」の話
さて、ここで冒頭の話に戻りましょう。
決してアメリカ人の歌が上手ではないと言っているのではないので、
くれぐれも誤解のないようにお願いしますね。
2012年ごろ、プロンテストの教材作成において、
英語の歌を収録する必要がありました。
簡単な英語の歌なので、
音符を見れば誰でも歌えると思ったのですが、
アメリカやオーストラリア出身の講師たちも、
プロのナレーターの方たちも皆、「音符が読めない」というのです。
日本では、小学校で音楽の時間に、
リコーダーを吹き、歌を歌うために楽譜を読みますね。
だからある程度、音符は読めています。
しかし、彼らは読めないと言いました。
教わらなかったと。
いやいや・・・
だって、アメリカ人も歌は歌うでしょう。
カラオケだってアメリカでも流行っているんだし。
そこで、調べてみると、
州ごとに異なるものの、たとえばテキサス州の教育基準では、
2年生で「5音音階の旋律パターンを標準的な読み書きし、
再現することなどが明記されていました。
(イリノイ州の教育委員会の資料)
にもかかわらず、実際には教師や授業方針によって差が大きく、
音符を体系的に学ばない、または習得できないまま
大人になる人も多いことがわかってきました。
・授業や担任による差:
音楽専門教師がいな学級担任の授業では、合唱やリコーダー中心で
「実演はするが楽譜の読み方は重視しない」ケースがある
・自主学習にゆだねられる:
興味のある子は音符を覚えようとするが、多くは隣の子にドレミを
書いてもらうなど、独学や他者依存の傾向もある
・学年による進行とのずれ:
低学年では難しいと判断し、教えられなかった。
または、中高学年になっても体系的な指導がなかったという報告も
教師側の経験値や実際の授業内容と指導要領との差。
つまり、
州や国レベルの指導要領には「音符の読み方を教える」となっていても、
現場の教師の力量・教育方針・学校の環境によって必ずしも実行されない、
そのギャップが「音符が読めないアメリカ人」を生んでいたのです。
◆日本の英語教育と同じ構図
そうです!
これはまさに、日本の「発音記号」の扱いと同じ構図です。
日本の英語教育に置き換えると、長年、教科書には発音記号も
書かれていましたし、大学入試にも「発音が異なる単語を選べ」
という問題が出ていた時代もありました。
教科書に発音記号が書かれていても、
先生がそれを指導できなければ生徒は学べません。
大学入試で必要とされなければ、先生方は教えません。
大学入試に発音に関する出題があった時代もありましたが、
政策や入試改革の影響で発音指導は揺れ続けてきました。
大学入試から「発音に関する出題」が消えた件については、
また別のメルマガでお話ししましょう。
しかし本来、私たちが目指すのは「通じる英語」です。
カタカナ発音のまま何年も学んでも、
相手に理解されなければ意味がありません。
◆プロンテストの使命
プロンテストはこれからも
「発音記号を基盤にした音声指導」を大切にしていきます。
世界では当たり前のように発音指導が行われています。
日本も「通じる発音」を学ぶ環境を整えることで、
ようやく世界に並ぶ英語力を育てられるはずです。
どうせ何年も学ぶなら、「通じる音」をしっかり身につけてほしい。
私たちはそのためのツールと指導を惜しみなく提供していきます。
いつか、「これぞ世界に通じる日本人の英語」と
胸を張れる日を実現するために!
株式会社プロンテスト
代表取締役 奥村真知
2025年9月 「発音クリニック」(オンライン)開催日程
A日程:
9月9日(火) 18:00〜20:00
9月16日(火)18:00〜20:00 (計4時間)
●発音訓練アプリ(6か月分)&「発音ロジック」オンデマンド講義 つき!
料金:30,000円
B日程:
9月20日(土) 9:00〜13:10 (計4時間)
●発音訓練アプリ(6か月分)&「発音ロジック」オンデマンド講義 つき!
料金:30,000円
C日程:
9月25日(木) 18:00〜20:00
10月2日(木) 18:00〜20:00 (計4時間)
●発音訓練アプリ(6か月分)&「発音ロジック」オンデマンド講義 つき!
料金:30,000円